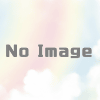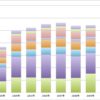還暦を迎えました

この写真は、2022年7月にジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope: JWST)が撮影した、560万光年先の銀河団の画像です(NASA, ESA, CSA, Kristen McQuinn (STScI) 提供)。宇宙戦艦ヤマトが目指したのは、地球から約16万8千光年離れた大マゼラン雲でしたから、この銀河団は遥かに遠方の宇宙に位置しています。
ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、このようなはるか彼方の深宇宙を観測するために開発された、赤外線観測専用の宇宙望遠鏡です。なぜ赤外線を使う必要があるのかというと、宇宙は加速膨張しているため、遠くの天体からの光は波長が伸びて赤方偏移を起こし、可視光線が赤外線域にずれてしまうからです。そのため、遠方宇宙の観測には赤外線が必須なのです。
では、なぜそのような遠い宇宙の観測が重要なのでしょうか。それは宇宙創生のメカニズムを解明するためです。
宇宙の成り立ちの解明は、1905年のアルバート・アインシュタインによる特殊相対性理論の発表に端を発します。さらに1915年、アインシュタインは一般相対性理論を提唱し、宇宙を静的で一定の大きさだと仮定しました。しかし、その方程式に矛盾が生じることに気づき、1917年に彼は方程式に「宇宙項(宇宙定数)」と呼ばれる項を追加して修正します。その後1929年、天文学者エドウィン・ハッブルが宇宙は膨張していることを観測的に示しました。この発見により、アインシュタインが導入した「宇宙項」は不要だったとされ、彼自身はこれを「人生最大の過ち」と悔やんだといわれています。
ところが1998年、ハッブル宇宙望遠鏡での遠方の超新星の観測を通じて、宇宙の膨張は一定ではなく、むしろ加速していることが判明しました。この加速膨張を引き起こしている未知のエネルギーが存在すると考えられており、それを「ダークエネルギー」と呼んでいます。近年では、このダークエネルギーがアインシュタインがかつて導入した「宇宙項」と一致するのではないかという見解が支持されています。
一方、20世紀以降は量子物理学・素粒子物理学も急速に進展しました。その結果、宇宙の始まりである「ビッグバン」(約138億年前)において、量子的な揺らぎが物質の不均一な分布を生み出し、それがやがて銀河や星を形成する「種」になったという理解が深まりました。また、1980年代以降には宇宙の法則を統一的に説明できるかもしれない「超ひも理論(超弦理論)」が登場しました。この理論が正しければ、ビッグバンの仕組みについても統一的に説明が可能になるかもしれません。
物理学は理論(数式による仮説)と観測(実験的検証)の両輪によって発展しています。超ひも理論は、私が高校生だった約40数年前には一般には知られていませんでしたし、JWSTのように深宇宙を本格的に観測する宇宙望遠鏡もまだ存在していませんでした。あれから40年余りが経った現在は、宇宙の根本的な原理がついに理論と観測の両面から解明されようとしています。いやコレは言い過ぎかな。超ひも理論の実証は、素粒子より小さい現象や高次元の存在を観測しなければいけないのですが、それは不可能なことのようです。とはいえ、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のような成果を見るとワクワクします。
ーーー
ココまでの話は、数年かけてブルーバックス、Newtonなどを読みかじって理解したものですが、もう少し踏み込んで理解したいと思うようになりました。還暦は通常なら定年退職なので、私もコレを機会に自分のスキを追求するオタクの道へ戻ろうと思います。
思い返せば幼稚園のときに、当時3ヶ月だけ住んでいた西武線ひばりヶ丘駅前の平屋の西友のブックコーナーで、初めて買ってもらった図鑑が「宇宙」でした(その光景は異様にはっきり覚えています)。我々の世代は宇宙に関心を持つしかない環境で、ウルトラマンシリーズ、アポロ計画、宇宙戦艦ヤマト、スター・ウォーズ、銀河鉄道999、機動戦士ガンダム、ボイジャー計画などが続いて、宇宙への好奇心を刺激されまくりました。
高校のときにNewtonが創刊されて購読したし、ブルーバックスも読みましたが、大学受験のために時間がなくなり、大学は別のことに集中して、社会人になったら仕事に没頭するようになり、そんな宇宙への興味は失われていきました。
50代でALSと共に生きるはめになりましたが、ここ何年かはスキマ時間に宇宙論や超ひも理論関連の本や動画を見るようになり、多少わかるようになりました。さすがに数式はちんぷんかんぷんですが、定性的な話が繋がり始めて、面白くなっています。特にChatGPTは、不明な事柄をすぐに深く調べられるので、理解を進めるのに大活躍しています。
ーーー
いつ還暦の話になるんだ、とお思いの方もいるかと思います。
わたしは30代の後半から、10年単位で自分の人生を振り返ったり、ゆるく方向を計画するようになりました。ざっと見てみると、
- 0代 とても発育が遅くてぼんやりした子どもで、学校のあらゆることについていけずに、コンプレックスを貯める時期でした。
- 10代 少し勉強がわかるようになり、テニスにも挑戦して、人並みになろうとする時期でした。
- 20代 自分が何者なのかを探り、ようやく自我がはっきりした時期でした。
- 30代 自分は技術で世間に影響を与える仕事をしたいと、もがく時期でした。テーマは大企業とアメリカというかシリコンバレーでした。
- 40代 自分の能力の限界を試す時期でした。テーマはベンチャー企業と中国でしたが、中国大連で子会社を作って経営しました。これは、私の人生の中で最も過酷な試練でした。しかし、夢半ばで降りることになり、会社に頼らないで一人で生きる道を選択します。
- 50代 当初は仕事の比率を徐々に減らして、世界遺産を巡る旅人になるつもりでしたが、ALSによる重度障害者として生きることになってしまいました。それでも、52歳のときに受けた誤嚥防止・気管切開手術の後に、やりたいことのイメージが降りてきて、7年あまりそれらを追求してきました。
ALSに対する世間一般のイメージからは信じ難いことかもしれませんが、体が動かない分サイズは小さいものの、目標をよく実現した7年あまりでした。また、一生関わることはないと思っていた行政の仕事に関わる機会も与えられました。
30ー40代の経験を活用すれば5年くらいでできるかな、と思っていましたが、下記2つがまだ終わっていません。
- ALS療養のノウハウを集めたデーターベースを作ること
- 自分の療養経験を整理して、まとめて発信すること
ALS学という分野横断的な学問体系があれば、もう学士くらいは取れるくらい、できることは学んで実行したかなと思っています。上記2つは卒論みたいなものですね。正直なところ10年やったので患者として生きるだけに飽きてしまい、もう区切りをつけたい。
これらは50代のうちに終えるつもりでしたが、スイス出張の影響からか昨年はずっと体調がすぐれずにいたため、なにもできずに過ごしました。すでに取りかかっているので、この1年で終わらせるように頑張ります。
ちょっとはみだしてはしまうものの、能力と器量の割には60年間よくやったなと思います。思考の緻密さと対人関係の感度がもう少し高ければ、もっと大きな仕事ができたかもしれないと思うこともありましたが、二人の息子も成人したし、もうコレで良かったと思うしかないですよね。
ーーー
そんなわけで60歳からは、普通のおじさんのようにリタイアよろしく、在野の宇宙研究家になります。研究成果を世間に発表することもあるかもしれませんし、全くないかもしれません。発表するときはペンネームにするので、もう私とはわからない形になるでしょう。
ただ、そのために ALS療養者としての発信はフェードアウトしていくだろうと思います。もうすでに「いいね」をつけるのはやめています。そのためにも、前述の2つのやり残しはさっさと片付けます。もちろん、ALS療養者として生きるための活動は続けますので、関係者の方はご心配なきよう。
そういうわけで、60歳以降も接点がある方は、どうぞよろしくお願いします。

学生ヘルパーズからプレゼントされた還暦トレーナを着て